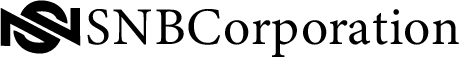
サービス一覧
- 原状回復工事
- リフォーム
- 内装工事
- 部分改修工事|Room Refine
- ハウスクリーニング
- キッチンフードクリーニング
- キッチンシンク・コンロクリーニング
- 浴室クリーニング
- エアコンクリーニング
- フロアコーティング
- A1フロアコーティングとは
- ブログ・お役立ち情報
施工事例
会社概要
お気軽にお問い合わせください!
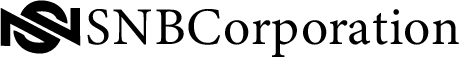
お気軽にお問い合わせください!

テナントの退去時に、貸主(オーナー)との間で最もトラブルになりやすいのが「原状回復」をめぐる問題です。
「通常の使用による汚れまで請求された」 「見積もりが不当に高額すぎる」 「敷金がほとんど返ってこなかった」
こうした問題は、原状回復に関する正しい知識がないために、テナント側が不利な条件を飲まざるを得ない状況から生まれます。しかし、法律やガイドラインに基づいた「正しい知識」で武装すれば、不当な請求に対して毅然と交渉し、ご自身の権利と資産を守ることが可能です。
この記事では、実際に起こりがちな4つの代表的なトラブル事例を基に、その問題点と、テナントが取るべき具体的な「法的対処法」を詳しく解説します。
トラブルの多くは、原状回復の基本原則に対する貸主と借主の「認識のズレ」が原因です。交渉を始める前に、まず以下の2つの大原則を再確認しましょう。

経年劣化
時間が経つことによる自然な変化や損耗。
(例)日光による壁紙やフローリングの色褪せ、畳の変色

通常損耗
普通に生活していて、自然に発生する傷や汚れ。
(例)家具の設置による床やカーペットのへこみ、テレビ裏の壁の電気ヤケ
これらは、家賃に含まれる「物件価値の減価分」と見なされるため、修繕費用はオーナー様が負担するのが原則です。

故意・過失による損傷
不注意や通常とは言えない使い方で生じさせた損傷。
(例)物を落としてできた床のへこみや傷、壁に開けたネジ穴
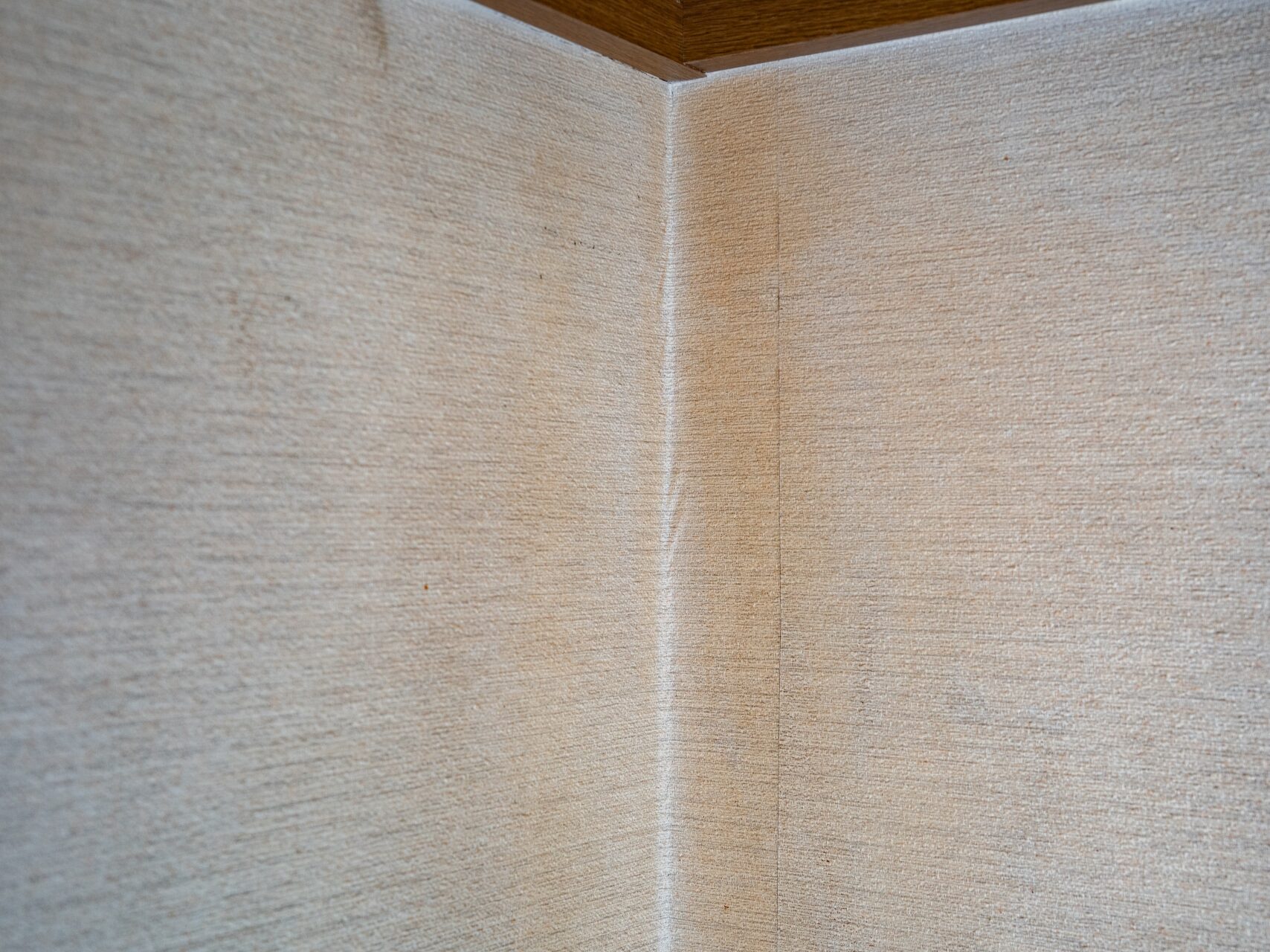
通常の使用を超える汚れ
掃除を怠ったことで発生・拡大した汚れ。
(例)タバコのヤニによる壁の黄ばみや臭い、結露を放置して発生したカビ、ペットによる柱の傷や臭い
これらの修繕費用は、入居者様に請求することが可能です。
この原則は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも明記されています。事業用物件では契約書の「特約」が優先されることが多いですが、このガイドラインが交渉のベースとなる重要な拠り所であることに変わりはありません。


【ありがちな主張】 「家具を置いていた床のへこみや、壁紙の日焼けもすべて元に戻してください。その費用は全額ご負担いただきます。」
【問題点】 家具の設置による軽微なへこみや、日光による壁紙の変色は、典型的な「通常損耗・経年劣化」であり、原則として貸主の負担です。テナントにこれらの費用を請求することは、ガイドラインの趣旨に反します。
【法的対処法】

【ありがちな主張】 「壁の一部分に傷をつけたので、壁全面のクロス張り替え費用として〇〇万円かかります。業者は当方で指定します。」
【問題点】 たとえテナントの過失による傷であっても、負担義務は原則として損傷した箇所のみ(最小施工単位)です。壁一面など、必要以上の範囲の修繕費を請求することは「過大請求」にあたります。また、貸主が指定した業者(B工事)の費用が、市場価格から著しく乖離しているケースも少なくありません。
【法的対処法】


【ありがちな主張】 退去後、何の連絡もないまま敷金が返還されない。問い合わせても「修繕費で全額相殺した」と、詳細な説明がない。
【問題点】 貸主は、敷金から原状回復費用を差し引く場合、その内訳を明記した精算書を借主に提示する義務があります。説明なく一方的に相殺することは認められません。敷金はあくまで「預けているお金」であり、その使途は明確にされなければなりません。
【法的対処法】

【ありがちな主張】 「この空調設備の移設はB工事なので、当方指定の業者しか使えません。費用は〇〇万円です。」と、交渉の余地なく高額な見積もりを提示される。
【問題点】 B工事(費用は借主負担、業者は貸主指定)は、ビル全体の安全管理上、必要な仕組みです。しかし、それを逆手にとって、競争原理の働かない閉鎖的な環境で不透明な費用が請求されるトラブルが後を絶ちません。
【法的対処法】
原状回復をめぐるトラブルの多くは、テナント側の知識不足や準備不足につけ込まれる形で発生します。しかし、「契約書」「ガイドライン」「入居時の写真」といった客観的な証拠を基に、法的根拠を持って交渉すれば、理不尽な要求を退けることは十分に可能です。
もし、当事者間での交渉が困難だと感じたら、決して泣き寝入りせず、内容証明郵便の送付や、弁護士、そしてSNBコーポレーションのような原状回復の専門家へ速やかに相談してください。正しい知識と行動が、あなたの正当な権利を守ります。


![]() 0120-429-172
0120-429-172
受付時間:10:00~18:00
![]() お問い合わせ・ご相談
お問い合わせ・ご相談
お気軽にお問い合わせください。
![]() 0120-429-172
0120-429-172
受付時間:10:00~18:00
![]() お問い合わせ
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
SNBコーポレーションは、愛知県・岐阜県・三重県を中心に、リフォーム・内装工事・フロアコーティング・ハウスクリーニング・原状回復工事など幅広いサービスを提供しています。

名古屋市を中心に、戸建て・
マンション・オフィスまで幅広い施工実績があります。
リフォームや内装工事、退去時の原状回復工事、日常のハウスクリーニングまで柔軟に対応可能です。
千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区
豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市・東郷町・大治町<
岐阜市や大垣市、多治見市など岐阜南部を中心に多数のご依頼をいただいています。賃貸物件の原状回復やリフォーム、フロアコーティングなど幅広い工事・清掃サービスを提供しています。
岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市
津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重北部エリアからのご依頼が多い地域です。住宅リフォームや内装工事、フロアコーティング、ハウスクリーニングなど安心してお任せいただけます。
津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市
お気軽にお問い合わせください。![]() 0120-429-172
0120-429-172