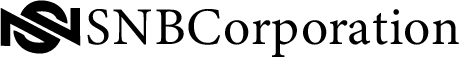
サービス一覧
- 原状回復工事
- リフォーム
- 内装工事
- 部分改修工事|Room Refine
- ハウスクリーニング
- キッチンフードクリーニング
- キッチンシンク・コンロクリーニング
- 浴室クリーニング
- エアコンクリーニング
- フロアコーティング
- A1フロアコーティングとは
- ブログ・お役立ち情報
施工事例
会社概要
お気軽にお問い合わせください!
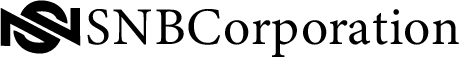
お気軽にお問い合わせください!
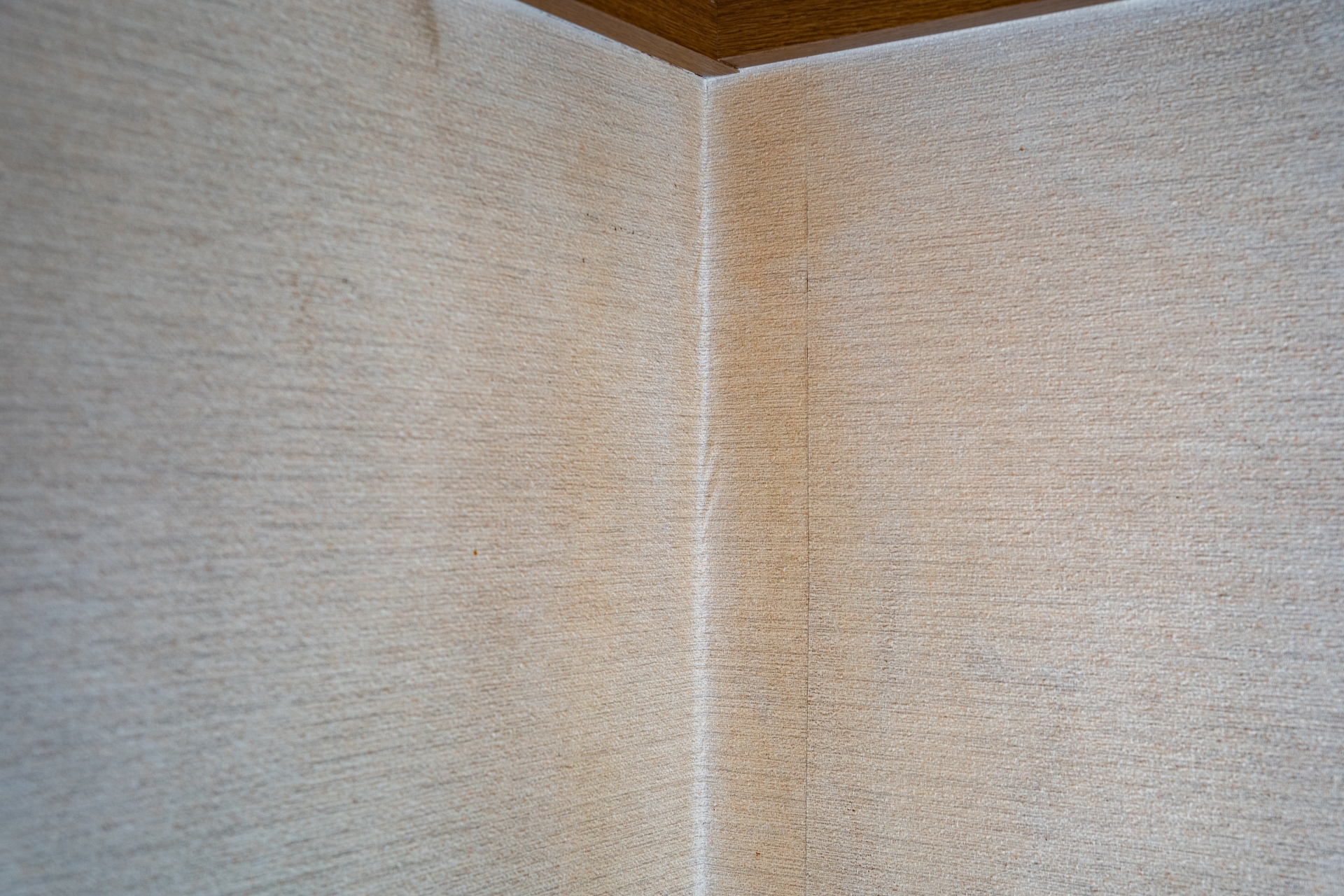
賃貸物件の退去時には、借主(入居者)は物件を原状回復して返す義務があります。これは契約上も法律上も重要なポイントであり、しばしば敷金の精算や修繕費用を巡ってトラブルになることもあります。特に「原状回復」という言葉は誤って「現状回復」と書かれることも多いため、正しい意味やルールを理解しておくことが大切です。本記事では、「原状回復とは何か」を賃貸契約の文脈で詳しく解説し、よくある誤解やトラブル事例、関連する法律の解釈、費用の目安や相談先までを網羅します。専門用語もできるだけわかりやすく説明しますので、借主・貸主双方にとって参考になる内容です。
まずは言葉の確認です。賃貸契約などで使われる「原状回復(げんじょうかいふく)」が正しい用語であり、これを誤って「現状回復」と表記してしまうケースがよくあります。原状回復とは文字通り「元の状態に回復する」という意味で、借りた当初の状態に戻すことを指します。一方、現状回復は「今の状態に戻す」という直訳になり、本来は意味が成立せず誤用**とされています。つまり、「現状回復」という言い方は間違いで、正しくは「原状回復」と覚えておきましょう。
なお、似た言葉に「原状復帰」や「原状復旧」がありますが、これらも「元の状態に戻す」という意味では原状回復とほぼ同じです。ただし「原状復帰」は主に建築・工事業界で使われる表現で、法律用語としては原状回復が一般的です。賃貸物件の契約書や法律では「原状回復義務」という形で規定されることが多いので、以降は原状回復に統一して解説します。
賃貸借契約では、契約終了時に借主が物件を原状に回復して返還する義務(原状回復義務)が定められるのが通常です。しかし重要なのは、「原状回復=入居前の新品同様の状態に戻すこと」ではないという点です。裁判所やガイドラインの考え方では、原状回復とは通常の使用による損耗を直すことではなく、借主の故意・過失などによる損耗・毀損を復旧することを意味します。言い換えれば、経年劣化や通常使用による傷みは借主負担ではなく、それを差し引いた借主の過失等による損傷部分を元に戻すのが原状回復なのです。
例えば、入居中に生活していれば避けられない「通常損耗」や「経年劣化」といった劣化は原状回復の対象外とされています。具体的には、家具を置いたことで生じた床のへこみ、冷蔵庫裏の壁紙の焦げ(電気ヤケ)、日光で焼けて色あせた壁紙や畳、ポスターやカレンダーを貼った跡(画鋲の穴)などは生活上通常生じ得る損耗であり、これらは貸主(大家)が修繕費を負担すべきものです。こうした通常の使用範囲での傷みについて、借主には修繕義務がなく、家賃にその分の費用が含まれているという考え方になります。

例えば、入居中に生活していれば避けられない「通常損耗」や「経年劣化」といった劣化は原状回復の対象外とされています。具体的には、家具を置いたことで生じた床のへこみ、冷蔵庫裏の壁紙の焦げ(電気ヤケ)、日光で焼けて色あせた壁紙や畳、ポスターやカレンダーを貼った跡(画鋲の穴)などは生活上通常生じ得る損耗であり、これらは貸主(大家)が修繕費を負担すべきものです。こうした通常の使用範囲での傷みについて、借主には修繕義務がなく、家賃にその分の費用が含まれているという考え方になります。

一方、借主の不注意や故意によって生じた「特別損耗」(通常の使用を超える損傷)は、借主が原状回復費用を負担するケースです。例えば、室内で喫煙したことで壁紙や天井にヤニ汚れ・臭いが付着した場合、通常の生活範囲を超える損耗として借主負担になります。その他にも、飲食物をこぼしたシミ、引っ越し作業でつけてしまった床や壁の傷、水回りのカビ(日頃掃除を怠った場合)、結露を放置して発生したカビやシミ、ペットによる柱や壁の引っかき傷・臭いなどは借主の過失による損傷**とみなされ、原状回復費用を借主が負担する典型例です。
原状回復のポイント: 国土交通省のガイドラインでも原状回復の考え方として、
(1) 通常使用による損耗や経年劣化は借主負担としない、
(2) 借主の故意・過失・善管注意義務違反による汚損・損傷は借主負担とする、
(3) 通常の使用を超えるような使い方で生じた損耗・毀損も借主負担とする、 の3点が明記されています。
つまり「原状回復=借主の責任で生じた劣化部分の復旧」と理解すると分かりやすいでしょう。
原状回復義務は法律上も規定されており、2020年施行の改正民法によってその範囲が明文化されました。改正後の民法では、賃借人(借主)は原則として賃借物の原状回復義務を負うが、通常損耗や賃借人の帰責事由によらない損傷についてはその義務を負わないとされています。これは従来の判例で確立していた考え方を法律に明記したもので、通常の使用による劣化は借主の負担から除外することがはっきり示されたものです。したがって、貸主から過剰な修繕費を請求された場合でも、それが経年変化や通常損耗の範囲内であれば法的には借主に支払い義務がないと言えます。
民法上は他にも、借主には物件を丁寧に扱う義務として善良な管理者の注意義務(善管注意義務)が規定されています(民法第400条)。これは「借りた物を社会通念上相当の注意をもって使用しなければならない」という義務で、賃貸住宅の場合、日常的な清掃や手入れも含まれま。もし借主がこの義務に反して不注意により通常以上の損傷を与えた場合、その損害は借主の責任となり、原状回復費用を負担することになります。例えば、水回りの掃除を長期間怠ってカビだらけにしてしまったり、タバコの火の不始末で床に焦げ跡をつけてしまったりすれば、善管注意義務違反として修繕費を請求される可能性があります。
法律以外にも、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が原状回復の一般的なルールを示しています。このガイドラインは、賃貸住宅退去時の敷金トラブル防止のために1998年に初めて策定され、2004年および2011年に裁判例の蓄積等を踏まえて改訂されたものです。ガイドラインでは原状回復について前述した裁判所の考え方を取り入れ、「原状回復は借主が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確にしています。そして原状回復を「借主の居住・使用によって生じた建物価値の減少のうち、借主の故意・過失(善管注意義務違反)その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しました。また、経年変化や通常の使用による損耗の修繕費用は家賃に含まれるものとし、借主負担としないことも明記しています。このように法律とガイドラインの両面から、「借主の責めに帰すべき損傷だけを元に戻せば良い」という原状回復の正しい解釈が示されているわけです。
なお、賃貸借契約書において特約事項で原状回復の負担範囲を独自に定めている場合があります。ガイドラインは法律ではなくあくまで目安なので、契約書で交わした内容が基本的には優先します。例えば「退去時にハウスクリーニング費用◯円を借主が負担する」といった特約があれば、特に不当な金額でない限り有効と判断されるケースもあります。そのため契約締結時には、原状回復に関する特約の有無や内容をよく確認し、納得して契約することが重要です。

原状回復費用をめぐるトラブルは後を絶ちません。典型的なのは、退去時の敷金精算で貸主側が請求する修繕費用の範囲や金額に借主が納得できず争いになるケースです。例えば、「畳をすべて表替え・交換した費用」「全面的な壁紙クロスの張替え費用」「鍵の交換費用」等を敷金から差し引かれ、借主が「そこまで負担する義務はないはずだ」と主張して揉める・・・これは原状回復トラブルの典型でしょう。特に経年劣化か故意過失かの線引きは争点になりやすく、貸主・借主の認識が食い違うとトラブルに発展します。
よくあるトラブル事例をいくつか挙げます:
こうしたトラブルを未然に防ぐために、借主側でできる対策・心構えをまとめます:
それでも話し合いで解決しない場合、第三者機関に相談する方法もあります。各地の消費生活センター(消費者ホットライン)では賃貸の敷金・原状回復トラブルの相談に応じており、解決に向けた助言や必要に応じて貸主への連絡をしてくれることもあります。また、業界団体である日本賃貸住宅管理協会にも無料相談窓口があり、賃貸借に関する専門知識を持つ相談員がアドバイスしてくれます。それでも解決しない深刻な事例では、弁護士に相談・依頼することも検討しましょう。弁護士に依頼すれば代理人として交渉や必要なら訴訟対応も行ってくれます。法テラス(日本司法支援センター)を通じて無料相談を受けることもできますので、トラブルが深刻化したら専門家の力を借りるのが安心です。

原状回復にかかる費用は、修繕箇所や損傷の程度によって大きく異なります。軽微な補修で済むのか、一部屋まるごとの交換が必要かによって金額は変わりますが、以下に代表的な項目の費用相場を紹介します。
以上のように、原状回復費用は内容によって様々です。賃借人が負担すべき費用については、国が定めた基準(ガイドライン)や民法のルールがありますので、不当に高額な請求を受けたと感じたらその基準に照らして交渉することができます。実際、敷金トラブルの相談では「交渉次第で費用が減額できた」という事例も多く、ある調査では交渉せずに支払った場合の平均約99,000円が、交渉した場合は約72,000円に減額されたという報告もあります。
最後に、原状回復トラブル時の相談先についてまとめます。まず身近なのは各都道府県や市区町村にある消費生活センターです。消費生活センターでは賃貸住宅の退去費用に関する年間1万件以上の相談が寄せられており、相談員からアドバイスを受けたり、必要に応じて貸主側への是正要請をしてもらえます。次に、不動産業界の団体である日本賃貸住宅管理協会(日管協)が設置している相談窓口も利用できます。賃貸管理のプロが無料で相談に応じてくれるため、契約や法律の専門的な質問も含めて頼りになるでしょう。また、各地の宅地建物取引業協会や不動産公正取引協議会などが敷金・原状回復に関する相談会を開催している場合もあります。問題が深刻な場合や法的手続きが視野に入る場合は、迷わず弁護士に相談してください。不動産問題に強い弁護士であれば適切なアドバイスや交渉代行をしてくれますし、法テラスを利用すれば所得に応じて費用の立替え制度なども利用可能です。

まとめ: 原状回復とは、賃貸物件を退去する際に「借りた当初の状態に戻すこと」ですが、その本質は「入居者の責任によって生じた劣化部分を元に戻すこと」です。時間の経過や通常の生活による消耗は借主の負担には含まれず、敷金はそうした部分の修繕費用を除いたうえで清算されるべきものです。貸主・借主の認識違いやコミュニケーション不足からトラブルが起きやすい分野なので、契約時から退去時までお互いによく確認をし、ガイドラインや法律を踏まえて冷静に対処することが大切です。万一トラブルになっても公的な相談先がありますので、一人で抱え込まず専門機関を頼って解決を図りましょう。
![]() 0120-429-172
0120-429-172
受付時間:10:00~18:00
![]() お問い合わせ・ご相談
お問い合わせ・ご相談
お気軽にお問い合わせください。
![]() 0120-429-172
0120-429-172
受付時間:10:00~18:00
![]() お問い合わせ
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
SNBコーポレーションは、愛知県・岐阜県・三重県を中心に、リフォーム・内装工事・フロアコーティング・ハウスクリーニング・原状回復工事など幅広いサービスを提供しています。

名古屋市を中心に、戸建て・
マンション・オフィスまで幅広い施工実績があります。
リフォームや内装工事、退去時の原状回復工事、日常のハウスクリーニングまで柔軟に対応可能です。
千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区
d
d
d
豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市・東郷町・大治町<
岐阜市や大垣市、多治見市など岐阜南部を中心に多数のご依頼をいただいています。賃貸物件の原状回復やリフォーム、フロアコーティングなど幅広い工事・清掃サービスを提供しています。
岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市
津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重北部エリアからのご依頼が多い地域です。住宅リフォームや内装工事、フロアコーティング、ハウスクリーニングなど安心してお任せいただけます。
津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市

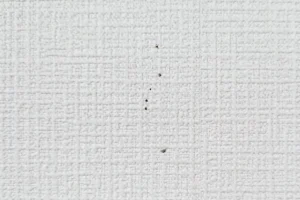






お気軽にお問い合わせください。![]() 0120-429-172
0120-429-172