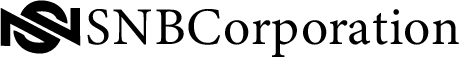
サービス一覧
- 原状回復工事
- リフォーム
- 内装工事
- 部分改修工事|Room Refine
- ハウスクリーニング
- キッチンフードクリーニング
- キッチンシンク・コンロクリーニング
- 浴室クリーニング
- エアコンクリーニング
- フロアコーティング
- A1フロアコーティングとは
- ブログ・お役立ち情報
施工事例
会社概要
お気軽にお問い合わせください!
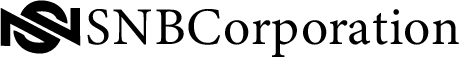
お気軽にお問い合わせください!

賃貸契約で「敷金償却」という言葉を目にしたことはありませんか?敷金という言葉には馴染みがあっても、「敷金償却」が何を意味するのか戸惑う大家さんも多いのではないでしょうか。実際、退去時に借主から「できるだけ部屋を綺麗に使ったのに敷金が全然返ってこないのはなぜ?」とクレームを受けてしまい、トラブルに発展するケースも見られます。こうしたトラブルを防ぐには、敷金償却の仕組みを正しく理解して契約時にしっかり説明しておくことが重要です。
本記事では、敷金償却とは何かという基本から、その法律上の扱いや会計処理(勘定科目・消費税)、さらに敷金トラブルを防ぐポイントまで徹底解説します。敷金償却を正しく理解し適切に運用すれば、原状回復費用を巡る大家・借主間の揉め事を減らし、賃貸経営をスムーズに進めることができるでしょう。ぜひ最後までお読みいただき、安心・安全な賃貸契約に役立ててください。
まず、敷金償却の意味を理解するために、通常の敷金との違いを整理しましょう。敷金償却は敷金と並ぶ重要な契約条件ですが、この2つは返金条件が大きく異なります。
入居時に借主から預かる担保金です。家賃滞納や退去時の原状回復費用に充て、残りは退去時に借主へ返還するのが原則です。つまり敷金は「いったん預かるが基本的に返すお金」です。
預かった敷金のうち「退去後も返さなくてよい」と契約で定めたお金を指します。修繕費が実際にかからなくても契約上返還しない特約になっている点が特徴です。契約書に明記した一定額を敷金から差し引き、その差額分は借主に返さない取り決めです。敷金償却の部分は最初から返還を前提としないため、敷金とは根本的に異なります。
なお、「礼金」は敷金と異なり入居時に貸主へ支払う一時金で全く返ってこない点では敷金償却と似ていますが、その性質は異なります。礼金は「貸してくれてありがとう」という謝礼的な費用であり(歴史的には住宅不足時代の名残)、契約時に支払ってしまえば原状回復費用には充てられません。一方、敷金償却はあくまで敷金の一部であり、将来発生する原状回復費の担保・精算という役割があります。
敷金償却=敷引き? 地域によって用語が異なる場合もあります。特に関西地方では敷金のことを「保証金」と呼び、その一部を返さない特約を「敷引き」と呼ぶ慣習があります。例えば「保証金30万円・敷引き10万円」といった契約では、退去時に借主がどんなに綺麗に使っていても10万円は返還されない仕組みです。関東で使われる「敷金償却」も同様に、契約時に予め返さない金額を定める制度で、主に家賃◯ヶ月分といった定額が償却されるケースが多いです。呼び方は違っても基本的な考え方は同じであり、契約書で償却金額(敷引金)が具体的に明示されます。
敷金償却特約が付いた契約では、借主から見ると「敷金を支払っても一部(場合によっては全額)が戻ってこない」ことになります。
たとえ退去時にほとんど修繕費用がかからなくても、契約で定めた償却額は返金されません。
裏を返せば、償却額の範囲内で原状回復工事が収まった場合、貸主はそれ以上の費用請求はできません(それを超える損耗があれば追加請求し得る)。このように敷金償却は、敷金の最低○円分は必ず差し引かれることを意味します。普通の敷金では原状回復費用を差し引いた残額が戻りますが、敷金償却では差額が発生しても戻らない点が大きな違いです。
実際問題として、敷金は多くのケースで全額が返金されていない現状があります。
ある調査によれば、東京では敷金が100%戻ってくる人はわずか12%で、約3割の借主は敷金が一切返ってこなかったというデータもあります。
平均でも敷金の返還率は42%程度に留まり、2ヶ月分の敷金を預けても1ヶ月分も戻らない例が多いのです。つまり借主にとって「敷金は全額返るとは限らない」どころか、半分以上戻ってこないことが珍しくありません。この理由には、実際の原状回復費用の差し引きだけでなく、契約上あらかじめ償却と定められた敷金が存在することも関係しています。敷金償却の制度を理解せず「敷金は当然返ってくるもの」と思い込んでいると、退去時に予想外の出費となりトラブルにつながるのです。
それでは、なぜ貸主は敷金償却という特約を設けるのでしょうか。敷金償却には、主に原状回復費用の確保と契約上の調整という2つの目的があります。
敷金償却で差し引いたお金は、多くの場合退去後のハウスクリーニング代や修繕費用に充てられることが前提です。あらかじめ「最低これだけは部屋の修繕費として頂きます」という形で設定することで、貸主にとっては将来の修繕費用を確保する保険のような役割を果たします。特に入居者の使用状況によって大きく費用が変わり得る場合(喫煙やペット飼育など)、敷金償却によって一定額を先取りしておくことで退去時の精算トラブルを減らす効果があります。

例えばペット可物件では、通常の使用よりも壁や床の傷・臭い清掃費が高額になる傾向があるため、「ペット飼育時は敷金+1ヶ月(償却)」といった追加条件を付ける例が一般的です。これはペットによる損耗リスクに備えて敷金を積み増しし、その一部または全額を返金しないことで、将来的な原状回復費用をカバーする狙いがあります。貸主側からすれば、マナーの悪い入居者がいた場合でも十分な修繕費を確保したいという心理が働くため、ペット飼育者には予め高めの敷金償却設定をしておくと安心なのです。実際、ペットあり物件で敷金償却の特約を設けておくことは、退去時のトラブル回避に大いに有効だとされています。

敷金償却は、契約条件上の調整として活用される場合もあります。その代表例が「礼金ゼロ物件」と敷金償却の組み合わせです。首都圏では近年、初期費用を抑えるために礼金なしの物件も増えています。しかし礼金ゼロは借主にとって魅力的でも、貸主にとっては本来得られるはずの一時収入(礼金)が無くなるデメリットがあります。
そこで、礼金をゼロにする代わりに敷金の一部を償却とする契約が考えられます。例えば「礼金0・敷金2ヶ月(うち1ヶ月償却)」という条件にすれば、入居時の現金負担は礼金0で軽く見せつつ、最終的には家賃1ヶ月分相当が貸主の収入となるわけです。
このような敷金償却は実質的に“後からもらう礼金”のような意味合いを持ちます。貸主にとっては礼金と同等の利益を確保できるメリットがありますが、借主からすると敷金だと思っていたお金が戻らない点で混乱や不満の原因にもなりかねません。実際に「礼金ゼロだから得だと思ったら、敷金が返ってこないなんて聞いていない」といったクレームが起きるケースもあります。このため、礼金ゼロ物件では他の費用(敷金償却など)が発生し得ることを契約時に丁寧に説明する責任が一層重要だと指摘されています。初期費用を抑えたい借主ほど後の費用トラブルが起きやすいため、敷金償却を設定する際は通常以上に丁寧な説明が必要と言えるでしょう。
物件によっては、「敷金全額償却」すなわち敷金=実質的な権利金として扱われるケースもあります。特にごく短期間(数ヶ月~1年程度)の賃貸や、家具付き高級賃貸などでは、敷金を退去時返還しない前提にして契約することもあります。これは短期利用による消耗や、高付加価値物件の使用料として最初から敷金を収入計上する考え方です。こうした契約では月々の賃料を割安に設定する代わりに敷金償却で調整するなど、契約全体のバランスを取る手段として償却特約が用いられることがあります。
地域的な慣習としては、前述の関西の敷引きが有名ですが、九州など西日本では敷引き文化が根強く残っています。一方、首都圏でも近年は礼金ゼロやペット可物件増加に伴い、敷金償却の特約が付く契約も散見されるようになりました。借主・貸主双方が納得ずくであればメリットのある制度ですが、不透明なままだと「知らなかった」「聞いていない」というトラブルの火種になり得る点に注意が必要です。
敷金償却の特約について、借主側から「返金されないなんて違法では?」と疑問が出ることがあります。結論から言えば、敷金償却特約そのものは法律上原則有効とされています。実際、2011年(平成23年)の最高裁判決において「敷引き特約(敷金償却契約)は原則として有効」との判断が示され、敷金償却条項は適法であるとの立場が確認されました。つまり、契約書に敷金償却の取り決めがあり借主が合意していれば、その特約に従って敷金を差し引いても法律的に問題はないということです。
しかし、だからといって無制限にどんな償却でも許されるわけではありません。判例やガイドラインから読み取れる、敷金償却特約が有効と認められるための条件を押さえておきましょう。
上記のポイントをクリアし、契約書に明確な条項があり、範囲・理由も説明の上で入居者の理解と同意を得ている場合には、敷金償却契約は有効となる可能性が高いとされています。判例主義の日本において最高裁の判断は強い指針となりますが、最終的には契約ごとの事情総合で判断されます。貸主としては「明確な合意」「過度でない金額設定」「合理的な理由説明」の3点を押さえておくことが肝要です。
敷金償却特約がトラブルとなり無効を主張される典型例としては、契約書に明記がなく説明不足だった場合や、償却額が非常識な高額だった場合などが挙げられます。また、敷金全額を無条件償却とする特約については、実際の損耗が軽微なときに裁判所から一部返還命令が出ることもあります。特に借主に過失がない通常の使用で生じる経年劣化部分まで償却対象とすると、「消費者保護の観点を欠く過剰な特約」とみなされかねません。
例えば、ある極端な例として「契約期間中いつ解約しても敷金は全額返還しない」という特約があった場合、入居者に全く非がなく短期間で退去しても一円も返らないことになります。これは貸主側に不当利得をもたらす恐れが高く、裁判になれば無効と判断される可能性が高いでしょう。実務的にも、そのような特約は借主から敬遠され契約自体が成立しにくいと思われます。
貸主としては、「敷金償却特約=万能な儲け手段ではなく、あくまで原状回復トラブルを防ぐための合理的な範囲で用いる」との認識が大切です。社会通念を超えるような過度な償却設定は避け、契約時には条項の意味と必要性を丁寧に説明しましょう。そうすることで、退去時に「聞いてない!」「納得できない!」といった争いを未然に防ぐことができます。
敷金償却の金額は最終的に貸主の収入となるため、適切な会計処理と税務対応が必要です。ここでは、貸主側の会計処理上のポイントと消費税の扱いを解説します。
貸主(大家さん)の立場で見ると、通常の敷金は将来返還することを前提とし預り金(負債)として扱います。一方、返還しないと決まった敷金償却分は貸主の「売上」(収益)として計上しなくてはなりません。基本的な勘定科目の考え方は次の通りです:
例えば、敷金10万円を預かり、そのうち契約上5万円を償却(返還しない)と定めていたケースを考えます。この場合、入居時点では10万円全額を「預り金」として処理します。退去時に償却5万円が確定したら、その5万円を「売上」に振り替え、残りの5万円を借主に返還します。結果的な仕訳は
①入居時「預り金10万円」→②退去時「預り金5万円減少・現金5万円支出(返金)+ 売上5万円計上」となります。
要するに、返さないと決まったお金の部分だけを収益認識するイメージです。
なお、敷金償却金がいつ確定するかによって収益計上のタイミングが異なる点にも注意が必要です。契約締結時に金額が決まっている場合は本来その時点で収益が予測できますが、通常は退去時まで貸主が自由に使えるお金ではないため、退去が完了し償却が確定した時点で収入計上するのが一般的です。一方、契約形態によっては「経過年数に応じて○割償却確定」など段階的に償却額が確定していく場合もあります。その際は契約で定めたスケジュールに沿って期ごとに按分して収益計上します。例えば「2年契約で敷金10万円のうち2年後に全額償却」と決まっているなら、1年目に5万円、2年目に5万円を売上計上するといった具合です。このように契約内容に応じて適切に期間配分しながら収益認識することで、税務上の問題も防ぎます。
敷金償却に消費税がかかるかどうかは、物件の用途によって異なります。居住用の住宅賃貸の場合、家賃自体が非課税取引であるため、敷金償却金も非課税(消費税対象外)として扱われます。一方、店舗・事務所など事業用物件の賃貸では家賃が課税売上となるため、敷金償却も課税取引(消費税の対象)となります。
では、課税となる場合の具体的処理を見てみます。契約時に償却金額が定まっているなら、その金額は将来的に貸主の売上となるため、消費税額を含めて計上する必要があります。たとえば「家賃20万円(月)・契約2年・敷金80万円(家賃4ヶ月分)・償却20万円(家賃1ヶ月分)」の事業用物件で考えてみましょう。このケースでは償却20万円が課税対象となり、消費税率10%で2万円の消費税が発生します。帳簿上は償却金を売上22万円(税込)として記入し、その内訳として消費税2万円を計上します。つまり、貸主は最終的に償却金20万円に対して課税売上を計上し、2万円を納税することになります。
重要なのは、消費税の課税/非課税の判断は物件が住宅用か事業用かで分かれる点です。居住用マンションやアパートの敷金償却なら消費税は心配いりませんが、オフィスや店舗の保証金償却ではあらかじめ消費税分も念頭に置いて契約金額を設定しないと、後で「税分の負担が抜けていた」ということになりかねません。契約時に消費税相当額をどう扱うかも含めて特約に盛り込んでおくと親切でしょう。
最後に、貸主側の会計処理に関連して税務調整の話を付け加えます。事業として賃貸経営を行っている場合、敷金償却で得た収入は不動産所得(法人なら営業収益)になります。当然、その分は確定申告や法人決算で収益計上しなくてはいけません。敷金償却は退去清算時にまとめて発生しやすいため、収入計上漏れや消費税申告漏れがないよう注意しましょう。会計処理が煩雑に感じる場合は、専門の税理士等に相談すると安心です。
敷金償却そのものは契約次第で有効に活用できる制度ですが、運用を誤ると借主との信頼関係を損ねるリスクも孕みます。「敷金償却=返ってこないお金」だからこそ、以下のポイントに留意してトラブル防止に努めましょう。
繰り返しになりますが、契約時の説明不足はトラブルの火種です。借主の中には「敷金は全額戻るもの」と思い込んでいる人も少なくなく、敷金償却の特約をきちんと理解していないと、退去精算時に「聞いていない」「違法では?」と紛争になる可能性が高まります。実際、敷金償却を巡るトラブルは近年増加傾向にあり、裁判沙汰に発展するケースも多々あります。
こうした事態を避けるために、契約締結時には以下の点を必ず借主に説明・確認しましょう:
また、契約書への署名時に特約事項の箇所を指差し確認してもらうのも有効です。「ここに○万円償却と書いてありますが大丈夫ですね?」と最終確認し、承諾を得ておけば後々「知らなかった」は言いにくくなります。小さな手間を惜しまず、契約時の一言で将来の大きな揉め事を予防しましょう。

敷金償却を導入する際に絶対に避けなければならないのが「原状回復費用の二重請求」です。具体的には、あらかじめ設定した償却額の範囲内で原状回復工事が収まったにもかかわらず、別途その費用を借主に請求してしまうケースです。例えば、敷金償却5万円の契約で退去時クリーニング代が4万円だった場合、本来その4万円は償却金5万円から充当されます。にもかかわらず貸主がクリーニング代4万円を別途請求すれば、借主からすれば「償却5万円取られたうえにクリーニング代まで請求された」と二重取りに感じられるでしょう。それは契約上も不適切であり、借主の不信感を招いてしまいます。
実際、「敷金償却=礼金と同じ」と誤解している貸主が、償却とは別に原状回復費を満額差し引こうとしてトラブルになる例があります。敷金償却の正しい理解がないと解約清算時に思わぬ争いを生み、最悪裁判沙汰になりかねません。そうならないために、償却金と原状回復費用の清算は厳密に区別して運用してください。契約書にも「償却金は○○費用に充当し、残額について精算」等の条項を設けておくと良いでしょう。借主には「この範囲までは敷金から頂き、超える場合のみ追加請求します」と事前に条件を明示することが大切です。
さらに、清算時には内訳の透明性も心がけましょう。敷金精算書を作成し、預り敷金から償却金○円、原状回復費○円を差し引いて返還額○円、といった明細を示すことで、借主も納得しやすくなります。国土交通省のガイドラインでも、通常損耗は借主負担にしない原則が示されています。経年劣化や通常使用による損耗分は請求に含めず、借主の故意過失による損耗や特約で合意した範囲内のみ負担してもらう姿勢が信頼関係維持には重要です。ガイドラインの範囲内であれば償却金も妥当性が説明しやすくなるでしょう。
敷金償却の設定額は前述のように社会通念上妥当な範囲に留めることが肝心です。特に初心者の大家さんは「償却額は大きいほど得」と考えがちですが、高額にすればするほど空室リスクも高まり、仮に契約できても揉める可能性が上がります。地域の相場や物件の競争力を見極め、適切な水準に設定しましょう。一般には家賃の1ヶ月分程度の償却なら借主の心理的抵抗も小さいですが、2~3ヶ月分となると敬遠される傾向があります(他に礼金等がなければ別ですが)。
万一、退去時に借主から敷金償却について異議が出た場合は、感情的にならず契約書とエビデンスに基づき冷静に対処しましょう。契約書にサインした以上原則有効であること、事前に説明していることを伝え、それでも納得しない場合は不動産会社や専門家を交えて話し合うのも一つの方法です。裁判に発展すると時間も費用もかかりますから、話し合いで解決できるよう誠意を持った対応が大切です。そのためにも日頃から記録を残す(説明資料や署名済み契約書控えの保管など)こと、トラブルが起きそうな兆候があれば早めに仲介業者等に相談することを心がけましょう。
敷金償却とは「敷金のうち契約で定めた分を返還しない特約」であり、将来の原状回復費用などに充てるための仕組みです。通常の敷金との違いは返還を前提としない点で、借主にとっては実質的な追加負担となる一方、貸主にとっては修繕費用の担保や礼金代わりの収入確保につながるメリットがあります。
法律的には敷金償却特約は適切な範囲で合意されていれば有効とされており、社会通念上妥当(おおむね家賃数ヶ月分以内)の金額で契約書に明記していれば問題ないと考えられています。ただし、金額が過大だったり説明不足で借主の理解を得ていない場合にはトラブルとなり、無効判断を受ける可能性もあります。重要なのは契約段階での透明性と合意形成です。
大家さん側では、敷金償却分は最終的に収入となるため会計処理や消費税対応も忘れずに行いましょう。住宅物件なら消費税非課税ですが、事業用物件では償却金に消費税がかかる点に注意が必要です。預り金と売上の振替処理や税務申告について不安がある場合は専門家に相談すると安心です。
敷金償却自体は決して借主を不当に困らせるためのものではなく、適切に使えば双方の安心につながる制度です。貸主としては、契約時の丁寧な説明と適正な特約設定によって、退去時の敷金トラブルを大幅に減らすことができます。借主の立場でも、敷金償却を理解して契約に臨めば「思っていたのと違う」という不満を避けられるでしょう。
最後に、敷金や原状回復を巡るトラブルは完全になくすことは難しいものの、知識と準備次第でリスクを最小限に抑えることは可能です。敷金償却に関する正しい知識を身につけ、契約時にしっかり確認・説明を行うことで、不当な費用負担やトラブルを防ぎましょう。もし敷金精算で行き違いが生じても、慌てず契約書と客観的な基準(ガイドライン等)に沿って話し合えば解決への道は見えてきます。
賃貸経営において信頼関係は何よりの財産です。敷金償却という制度を正しく活用し、借主にも納得してもらえる運用を心がけることで、円満で安心な賃貸契約を実現しましょう。万が一対応に悩む場合は、早めに専門家へ相談するなど適切なサポートを得ながら、健全な賃貸管理に努めてください。お問い合わせやご相談はお気軽にどうぞ。皆様の賃貸経営が円滑に進む一助になれば幸いです。

![]() 0120-429-172
0120-429-172
受付時間:10:00~18:00
![]() お問い合わせ・ご相談
お問い合わせ・ご相談
お気軽にお問い合わせください。
![]() 0120-429-172
0120-429-172
受付時間:10:00~18:00
![]() お問い合わせ
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。
SNBコーポレーションは、愛知県・岐阜県・三重県を中心に、リフォーム・内装工事・フロアコーティング・ハウスクリーニング・原状回復工事など幅広いサービスを提供しています。

名古屋市を中心に、戸建て・
マンション・オフィスまで幅広い施工実績があります。
リフォームや内装工事、退去時の原状回復工事、日常のハウスクリーニングまで柔軟に対応可能です。
千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区
d
d
d
豊橋市・岡崎市・一宮市・瀬戸市・半田市・春日井市・豊川市・津島市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・蒲郡市・犬山市・常滑市・江南市・小牧市・稲沢市・新城市・東海市・大府市・知多市・知立市・尾張旭市・高浜市・岩倉市・豊明市・日進市・田原市・愛西市・清須市・北名古屋市・弥富市・みよし市・あま市・長久手市・東郷町・大治町<
岐阜市や大垣市、多治見市など岐阜南部を中心に多数のご依頼をいただいています。賃貸物件の原状回復やリフォーム、フロアコーティングなど幅広い工事・清掃サービスを提供しています。
岐阜市・大垣市・高山市・多治見市・関市・中津川市・美濃市・瑞浪市・羽島市・恵那市・美濃加茂市・土岐市・各務原市・可児市・山県市・瑞穂市・飛騨市・本巣市・郡上市・下呂市・海津市
津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重北部エリアからのご依頼が多い地域です。住宅リフォームや内装工事、フロアコーティング、ハウスクリーニングなど安心してお任せいただけます。
津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・尾鷲市・亀山市・鳥羽市・熊野市・いなべ市・志摩市・伊賀市
お気軽にお問い合わせください。![]() 0120-429-172
0120-429-172